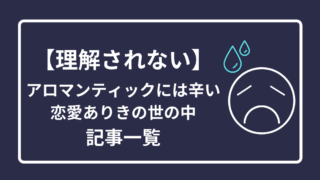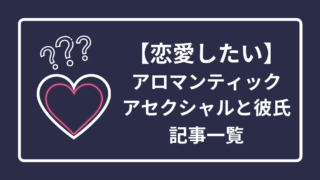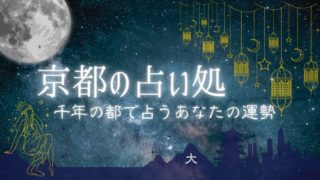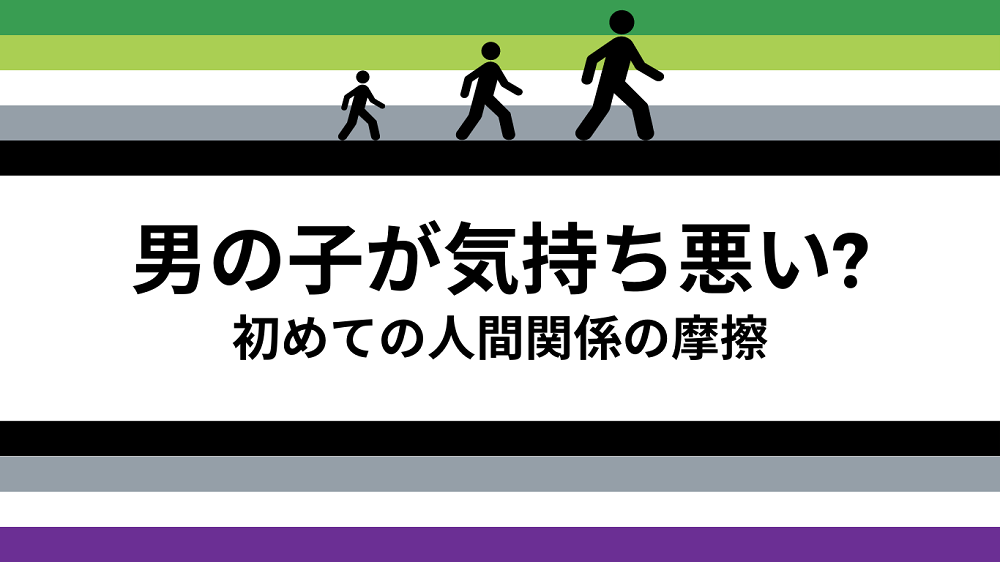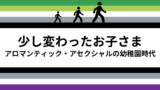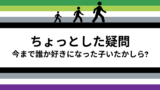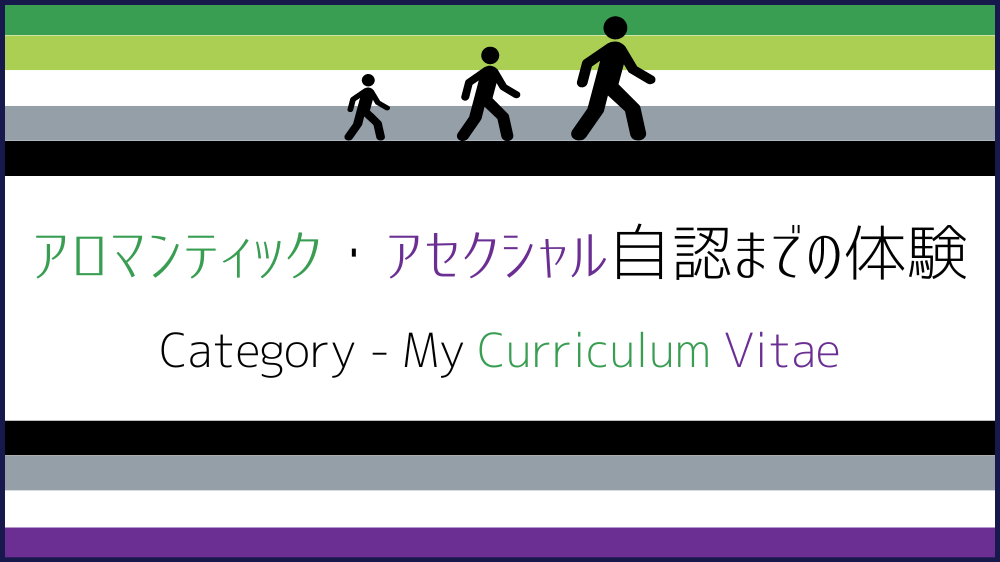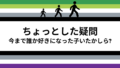幼稚園児の筆者は空気が読めないやら、1番ではないと嫌やらと、我儘極まりない園児をしておりました。
また、何と言ったら良いか・・・自分のことなので書いてしまいますが、

周囲とのズレを自分でも認識できるくらいだったので、何かそちらの気も当時あったのではないかと感じます。
そちらの気の話はほどほどに、世の中は現在の「多様性」からは、まだまだかけ離れている時代。
小学生の頃を思い返すと、安直ですが「ランドセル」が思い浮かびます。


少なくとも筆者が小学生の頃は、ランドセルの色は男の子は「黒」、女の子は「赤」、この2択でした。
他の色もあったかもしれませんが、この2択以外は基本考えられない。
この2色以外は、悪目立ちという表現の方が適当・性別と会わない色を持っていたら他者からの詮索の対象になったかと思います。
女の子が黒が良い、なんて言ったら親御さんから「女の子なんだから赤にしなさい、赤が普通でしょ」。
今となっては謎理論ですが、その当時は疑いもなく言われていたでしょうし、言われた側も疑問や不満を抱えながら赤いランドセルを背負ったと思います。
少数派の方への配慮はなく、現代では問題行為・発言として認識されそうなことが、やっと問題かもしれないと認識され始めてきた時代。
では幼稚園に引き続き、小学生の筆者は「どのような感覚を持っていたか?」大人になった筆者が分析してまいります。
わがまま幼稚園児が小学生になったら
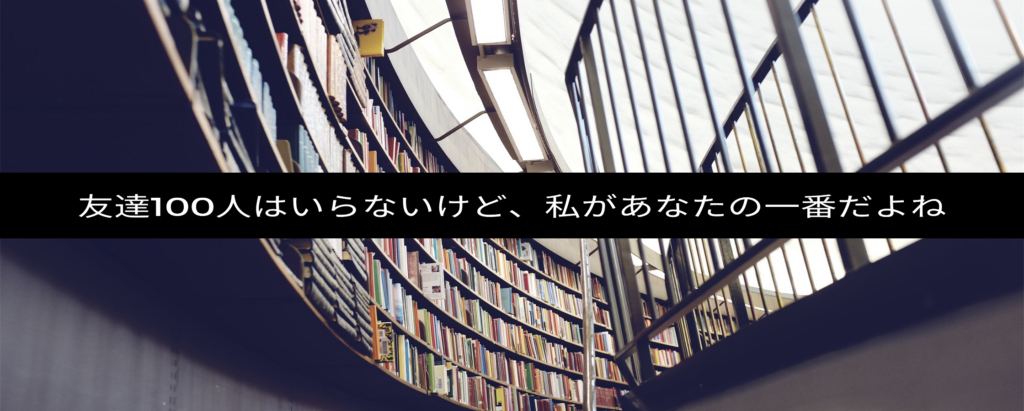
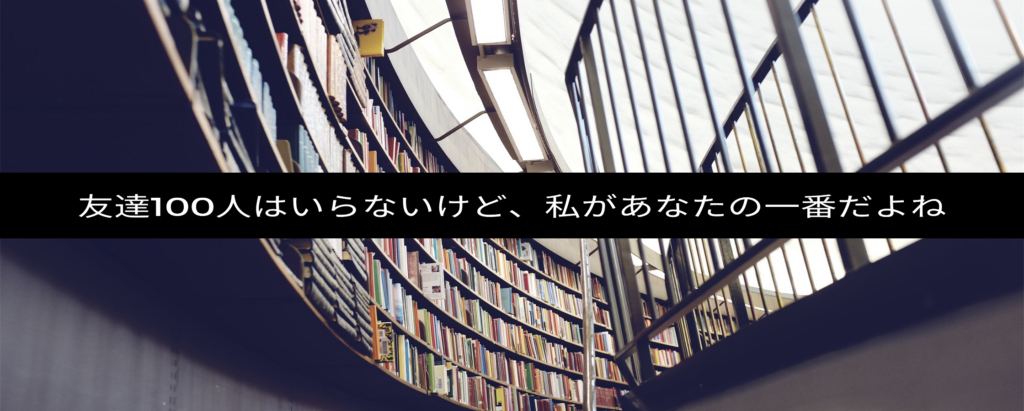
なかなかホラーテイストな言葉ですね「友達100人はいらないけど、私があなたの一番だよね」。
どこの拗らせたやつかと思ったら、小学生なりたてホカホカの女児が心からそう思っていたのです。


我が幼少期ながら、恐ろしい発想です。
自分でも少し変わっているなと自覚している幼稚園児が、小学校1年生になりました。
当時の筆者の執着の対象である、仲の一番良い友人も同じ小学校、おまけに同じクラス。
その当時の筆者からしてみれば、嬉しくて楽しみしかありません。
小学生になっても、引き継き変わったお子様
小学校、少なくとも2年生くらいまでは、幼稚園の頃の性質を色濃く残していたと思います。
どんな性質か簡単に言いますと、この通りです。
- 子供でも読む空気が読めない
⇒悪気はなく、色々とアレコレ考えたうえで発言するのですが、考え抜いて発した発言・起こした行動がどうも周囲とずれていました。 - 集中すると周りが見えなくなる
⇒悪意はありませんし、嫌がらせでもありません。でも結果、筆者が気付けなかったことになってしまいます。 - 仲の良い子への執着が恐ろしい
⇒私があなたの1番、それ以外ありえませんよね?この考え方だけは幼心に「なぜこんなに執着するのか?」と感じていましたが、執着の感情を止めることはできませんでした。
人によれば、子供なんだからそんなこともあるよ、とおっしゃる方もいると思います。
しかし、年を重ねるにつれて「私がずれてるな」と自覚するようになり、軌道修正にはかなり手間取ったものです。


大人になった今でも、考えた末に「あ、やべ。間違えたかも」となることも。
– 余談 –


この考えた末に選択を間違える技、今でもゲームで発揮することがあります。
自分が選んだ回答でストーリーが変わるゲームがあると思いますが、間違えるのです、筆者。
ヒロインの運命がかかった重要な選択肢を「皆ならこう考えるのでは?」「普通ならこうか?」と捩じ切れんばかりに考え抜いたうえで、選択肢を間違えます。
つらい① 友人への執着が止められない


これが1番感情をコントロールでずに、子供ながらにつらいと思った性質です。
自分でも「ちょっと変だよね?」と自覚していても、この執着やめたいと思っていても、執着の感情がどうしても止められなかった幼少期。
小学校へ入学して幾許か経った頃、この執着はさらに育っていました。
- 筆者以外の子と仲の良い友人が楽しそうに話しているのを見るのも嫌。
- 筆者を1番と思っていない友人にも苛立ち、友人と話している子にさえ激しい嫉妬をする。
嫉妬の種類も重さも増えて、子供ながらにつらく思う時がありました。


ちょっと、私をほっておいて何他の子と話しているの?あなたが1番仲が良いのは私でしょ!?


そこのお前もお前だ。その子と私が1番仲良いの知ってて、なに仲良くしてくれてるの。


おかしいけど、やめられない。やめたいのに、この執着が止められない。
この葛藤の結果としては、友人・友人と話していた子への激しい嫉妬やら怒りやらを燃やしつつ、
顔を引き攣らせながら、平静を装うようにしていたと思います。
ただ友人が別の子と話しているだけなのでに、なぜ、こんなに感情を揺さぶられるのか?揺さぶられなければならないのか?
こんなにも執着してしまう自分にも、子供ながらに些か嫌気がさしておりました。
つらい② 自尊心が間違った方向に急成長
執着もそうですが、なぜか一気に成長した筆者の自尊心。
これも友人への執着と同じく、自身が1番ではないと嫌という心の影響なのか?


とにかく負けるのが嫌で、負けることはありえない。特に、1番仲の良い友人に決して負けてはいけない。
筆者の執着の対象となっていた、1番仲の良い友人。
今も昔もこれからも、その友人本人に対して言いませんが、勉強においても何においても、1番の敵でした。
ライバルではなくあえて「敵」という言葉を使う必要があるくらい、すごく気にしていました。


友人は筆者のような心は持っていなかったと思います。
それが筆者なんか眼中にないと言ってるようで、勝手に1人で激しく苛立っていました。
当時、その友人と筆者は、勉強でも運動でも何かしたら大体同じか、どちらかが少し上。
負けた時、もしくは筆者が上回ったけど、友人が気にしていないように見えた時、これでもかと心の中は荒れ狂いました。


もっと悔しそうにしろや!私があなたに負けた時の気持ちと同じくらい、あなたの心も荒れ狂えよ!


なんで私だけが心をざわつかせなければならないのか!
すごく言い方が悪いのですが、恐らく筆者は1番仲が良いと言っておきながら、
自分より下に見たくて仕方がない、マウントをとりたくて仕方なかったのだと思います。
・・・うっわ、性格悪い。自分のことですが、これは面倒な子供。負けん気の強さを超えている気がしてなりません。
余談 – ランドセルの色は「青」が良かった
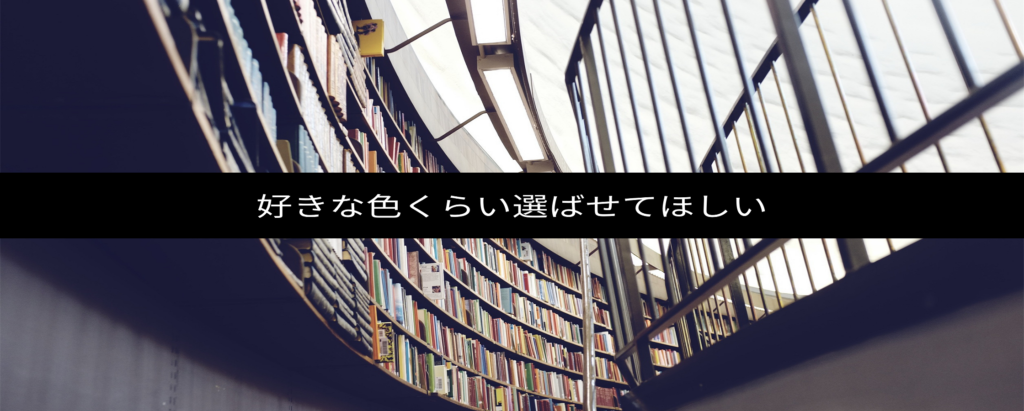
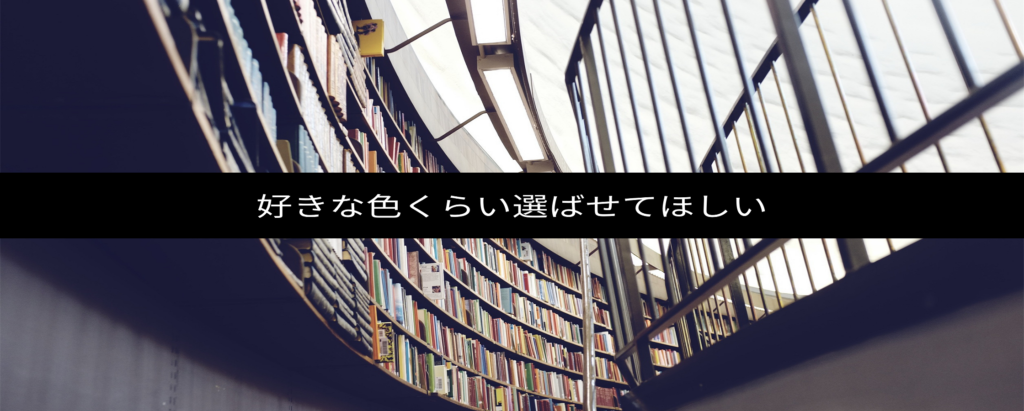
筆者の時代のランドセルの色は「黒」か「赤」、他の色も少しあったかもしれませんが、
それは悪目立ちするので避けるべき、位の感覚だったと思います。
特に男の子が女の子の色「赤やピンク」が欲しいと言ったら、女の子が男の子の色「青や黒」が欲しいと言ったら。
今ではありえない言葉を使った説得・否定の言葉が家族から飛んできたことでしょう。
ちなみに筆者が使っていたランドセルは例にもれず「赤」でしたが、


なぜ女の子だからって、赤なの?あたし、青が良いんだけど。


ねぇ、誰か決めたの?校則に書いてあるの?校則変えてもらうけど?
昔から戦闘民族です。。。
「よくある戦隊ものの主役の色は赤で男性なのに、なぜランドセルは女の子が赤と決められているのか?」と変でしかない、とは子供でも感じておりました。
また、幼稚園の頃の話でも書いた通り「性自認で違和感を覚えたことはない」のです。
この頃の筆者の怒りは「性別により色が決定されることへの疑問」より、
「自分が選びたいものを選べない」=「勝手に誰かの都合で既存の型にはめられた生活を強要されている」という方向性で怒っていたと思います。
世の中の当たり前・常識とされていることが、すべからく私もしくは世の中全ての人の、当たり前・常識だと思うなよ!と思ったのでしょう。
・・・可愛くない子供ですが、大人の筆者も思っているので、そこまで変なことは言っていないかな、と思うところです。
初めましての感覚 – 男の子が気持ち悪い?
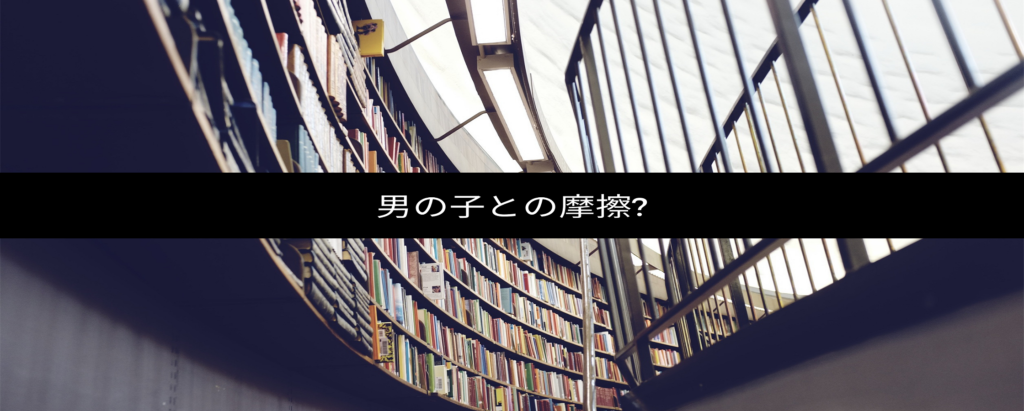
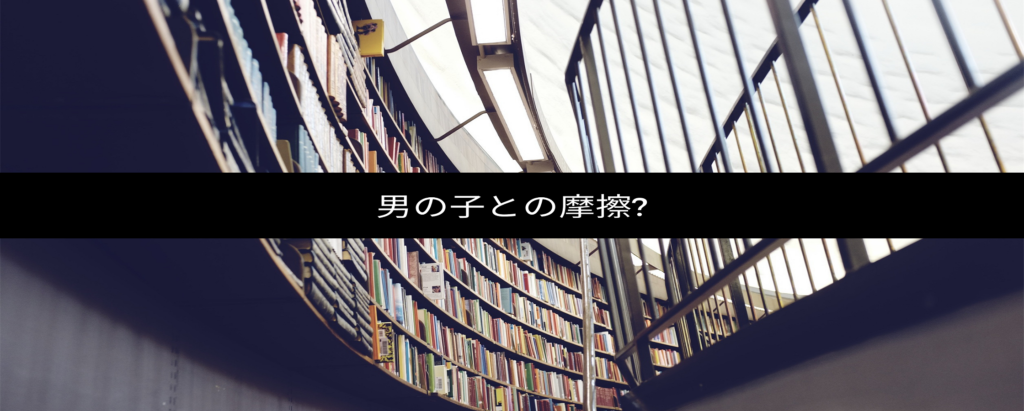
可愛くない性格をしていた小学校低学年の筆者ですが、小学1-2年生は人生最初で最後のモテ期でした。


この頃の筆者ですが、絶対零度の大人の眼差しで思い返しても、恐ろしいほどもてました。
これが余計に面倒な性格を助長させた要因のかもしれません。
少なくとも同じクラスの男の子は全て筆者の思い通りになる子である、と勘違いする程度にはもてました。
敵と言ってしまった仲の良い友人と筆者でダブル女王蜂です。(女王蜂は1匹で良いとも思ってもいましたが。。)
我が人生のピーク。
そんな振る舞いのつけが回ってきたのか、行いが悪かったのか、入学して少し経った頃、様子が変わり始めていきました。
筆者が戸惑った「つきまとい」
もてたことは、さぞ当時の筆者を気分よくさせたのでしょうが、初めて男の子を気持ち悪いと思うことがありました。
嫌な言葉を言われたとかではないし、粗野な態度をとられるとか、そういう類のものでは決してないのですが・・・


常に筆者を見ているけど、少し離れたところから、という男の子が一人いました。
何をされたかと言いますと(何もされていないのかもしれませんが)、当時の筆者が戸惑った行動はこんな感じです。
- 席替えをします!まず女の子、好きな席に座ってください。では次は男の子、好きな席に座ってください。
- 筆者の席の隣の席をめがけて走り出す当該男子。
- 意味がわからない。嫌がらせ?ってか、これで何回目?勘弁してほしい。意図が分からず気持ち悪い。
- 下校時、ずっと後をつけてくる。筆者の家の近くにきたら消える。
- 文字にして驚いた、これ駄目なやつですね。
基本的に、手を伸ばしたら届く範囲のやや外に佇み、筆者の動きにあわせて行ったり来たり。
友人やクラスメイトと筆者が話していても、その会話の輪にも入らないのですが、少し引いたところから、ずっと見ている男の子。
ただただ、意味不明でうっとおしく、気持ちの良いものではないと幼いながらに感じました。


今なら流石にこんなに拗らす前に動けますが、1年2年生の頃の自分には難しかったかもしれません。
他者との摩擦を知らなかったお子さま
一人っ子が全員そうとは口が裂けても言いませんが、喧嘩の仕方、良くも悪くも人との摩擦を知りませんでした。
- 親から怒られることはあっても、子供同士で喧嘩する経験がほとんどなかった。
- いとこには同世代もいましたが、筆者が1番年上でこちらでも女王蜂をしていたので、喧嘩をしたことがほとんどなかった。
- クラスでも女王蜂なので、間違いなく「あいつなんやねん」と言われていたでしょうが、男子が盾となり苦情の言葉も届かない。
「自分に悪意やそれに似た感情が向けられることを知らない」もしくは「そんな感情が自分に向けられるなんて想定すらできていない」筆者にとって、
何あの子、変。でも何て言ったらよいかわからない。なんであの子、こんなことするの?筆者の世界にはないので、よくわからない。
(気が強いのか弱いのかわからない)
本当に嫌であると誰に相談することもないまま、クラス替えが行われる2年生の最後まで、我慢したと思います。
それ以上に学校には楽しかったので、気になるけど、まあ、具体的に何かされたわけではないので、うん。。。といった感じでもありました。
この体験が今後自身の成長やものの考え方へどんな関りがあったのか、なかったのかは今でもわかりません。
ただ、男の子に対して「初めて嫌と思う気持ちが生まれた」のは確かです。


この男の子とはなぜか高校まで一緒で、最後の方は普通に話す仲でした。
まとめ
幼稚園児の頃よりも、磨きがかかったワガママ小学生の筆者。
当時はアロマンティックやアセクシャルという言葉はありませんでしたし、自身が恋愛感情を抱けない方面の人間とは気づいていません。
ただ、人生のポイントとして異性である男の子に対して、嫌と思う気持ちが生まれた時期でもありました。
誰でも一時期、異性に対して嫌だなと思う頃があるんじゃない?と言われたら、その通りです。
アセクシャルやアロマンティックと無理矢理結びつけるつもりはありません。
都合よく後付けの解釈だなと思ってしまうところですが、


この男の子との出来事は、アロマンティック・アセクシャルであることをより強化した気がする、と大人になった筆者が感じているくらいです。
さて続きの記事でも、引き続き小学校低学年の筆者について書いていきます。
初めて「好きな子言い合ってみよう!」の提案を男の子からされたことを思い出しました。