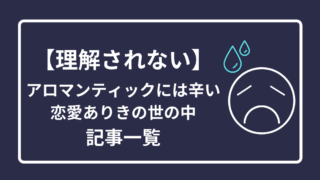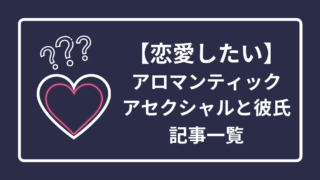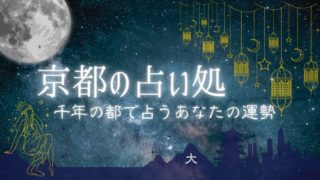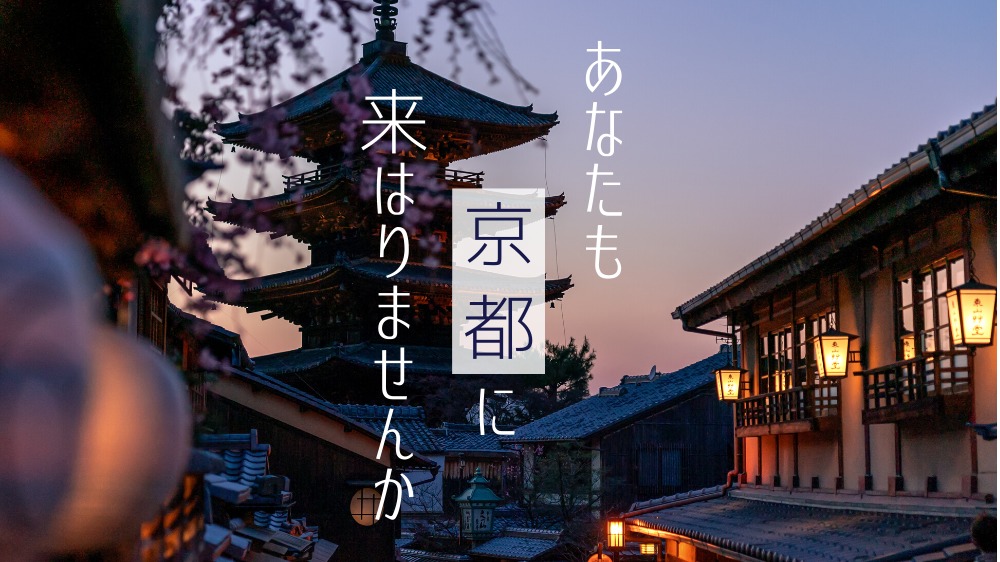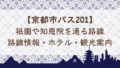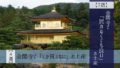– Category KYOTO –
京都市民が京都から発信する、春夏秋冬 京都の四季折々の「京都の楽しみ方」
京都旅行を計画中の方・決めた方・既にいらしている方が知っていたら「より深く京都を楽しめる情報」をお伝えいたします
ブックマークして、旅のお供にもしていただけたら嬉しいです
【旅マエ】京都のお宿


京都には宿泊施設・観光スポットなど見どころがたくさんあります。
宿泊について言えば「歴史が深い施設」「新しく京都に来てくれた施設」「大規模なものから一家族に限定されたもの」「外資系の華やかなホテル」や「和を感じさせてくれる旅館」まで、多種多様。
旅先として「京都」が候補に挙がっている方、京都の宿泊に関する情報が欲しい方は、ぜひご覧ください。
【旅マエ】京都観光情報


日ごろ京都市バスを使用していますが、路線の多さには些か辟易することも。
観光でいらいした方からすれば、尚更のこと。京都市バス路線に混乱している方も見かけます。
こちらを見たら、京都市バスの乗り方で迷うことはなくなるはず!と思いながら書きました。
「市内観光するうえで、市バスでの移動がストレスにならない」を目指して、路線・路線上の観光案内をお届けします。
観光地Tips!
交通Tips!
京都Tips!
市バス路線Tips!
【旅ナカ】観光地への行き方


宿泊地から観光地までの行き方は大丈夫。でも、観光地から別の観光地までの行き方がわからない!
京都市バスの路線は決して大きくない京都市内中心部に張り巡らされています。
地元の人でも自分が使わない路線は知らないことも多く、特に観光で来られた方はバス・鉄道含めて分かりにくいところが多いと思います。
こちらでは「主に京都市バスを使った観光地間の交通情報」(例: 二条城から八坂神社への行き方)をお伝えします。
【旅ナカ】買わなくても良いお土産
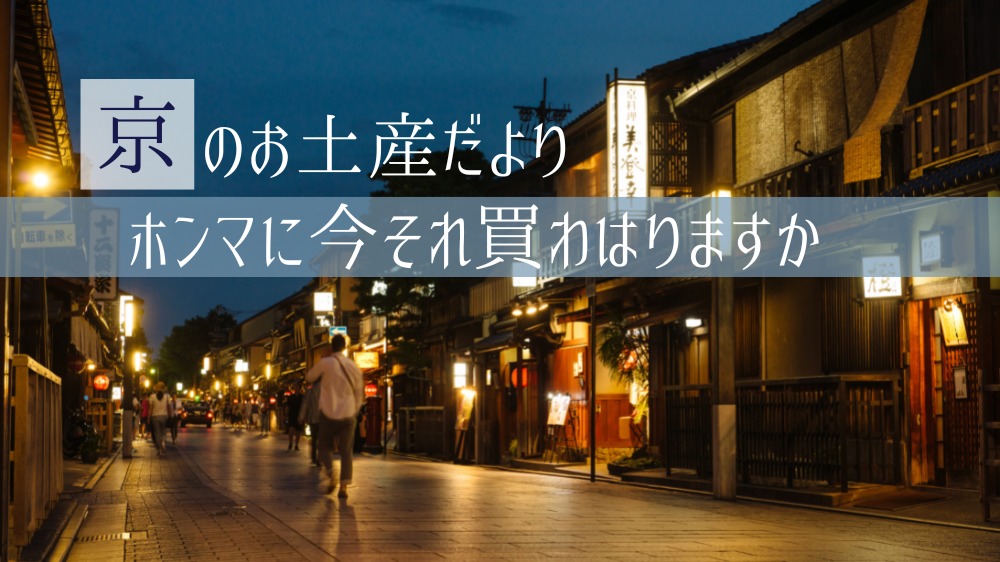
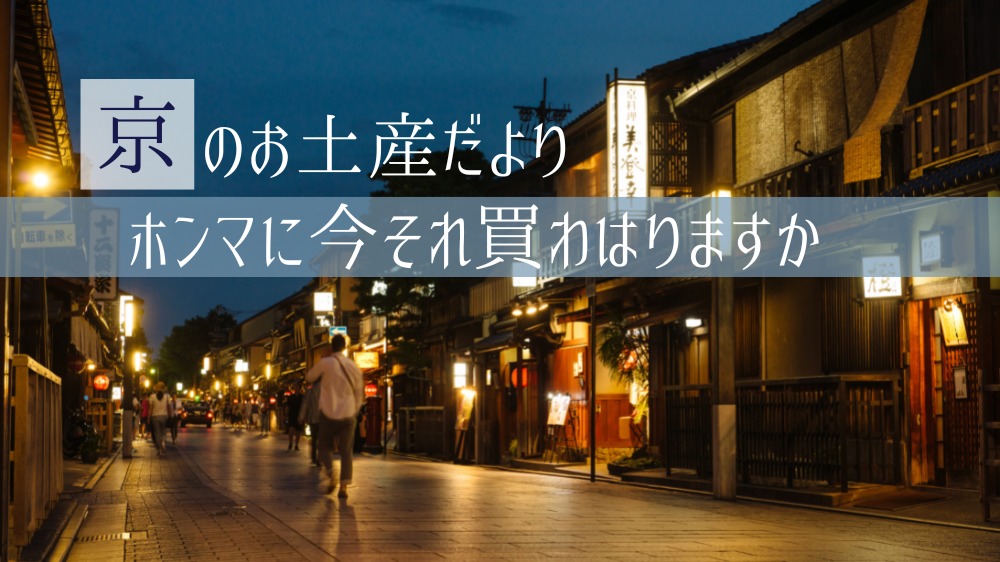
自分が欲しかったお土産・ご家族やご友人へのお土産、お土産の購入目的は色々。
お目当てのお土産が行った先で見かけたら、購入するのは自然の流れですが・・・
「手荷物が増えますけど、大丈夫ですか?」「今日の観光はおしまいですか?」
「そのお土産、京都駅でも買えますよ」
もし、そのお土産が今買わなくても良いお土産だったら・もし、京都駅などでも出会えるお土産だったら。
その観光地でしか買えないお土産・あえてその観光地で買わなくても良いお土産を紹介いたします。
買わなくても良いお土産情報
サイト名: 「京都フリー写真素材」「京都の桜フリー写真」
※本ブログの京都に関する記事の写真の一部は「京都フリー写真素材」様・「京都の桜フリー写真」様より頂いております。